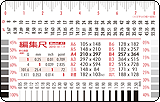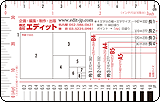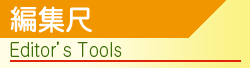
株式会社エディットは、2006年に「編集尺(へんしゅうじゃく)」というオリジナルアイテムを作成しました。
本づくりや編集作業に必要なツールを一枚にまとめた、便利なカードです。
紙寸法表や簡易級数表、網点・罫線スケールなどの機能を持っています。
エディットに来られたお客様や、社員がおじゃました会社様にお渡ししています。
また、東京国際ブックフェアなどの展示会でも無料配布しています。
ポケットに入る、“本づくりの七つ道具”です。
編集・DTP・印刷の各業務で、お役立てください。
編集尺の機能
-
センチメートル定規(簡易級数表)
- 簡易級数表として使用できます。
- メートル法と級数の関係は「1mm=4級=4歯」ですので、「1mm=1級×4字分の幅」です。
そのため、たとえば「20mm=20級×4字幅」ということになるので、「4字幅のmm値=級数」ということになります。
- 上述のような「簡易級数表」としての使い方は、ミリメートル目盛りの入った定規ならばどれでもできます。しかし、専用の定規ではないので、使いづらいことがあります。
そのため、この「編集尺」では、より読み取りやすくするため、目盛りの形を変えてみました。
→目盛りの長さを、すべて同じではなく、少しずつ変えて「山形」にしてあります。
-
4cm〜8cmの間は、よく見ると、0.5mm単位で小さな目盛りが入っています。
0.5mm単位というのは非常に細かく、普段は用いませんが、本づくりの作業の中では時折、必要になってきます。普通の形の目盛りを入れると、逆に測りづらくなってしまいますが、“ぎりぎりまで短くする”ことで対応しました。
普段は邪魔にならず、目を近づけると見えてくる、小さな目盛りです。
- メートル法と級数の関係は「1mm=4級=4歯」ですので、「1mm=1級×4字分の幅」です。
- 級数(Q)をベースに、対応するポイント数の一覧表です。
- 5%〜100%までの網点密度サンプルをカード左右に配しています。
-
印刷物においては、版式や印刷条件により異なりますが、網点が拡大(ドットゲイン)するため、一般的な条件下では網点の濃度は指定より若干濃くなる傾向にあります。
2006年版:編集尺「ver1.0」は、175線でポリスチレン系の特殊紙にスクリーン印刷で刷っているので、ドットゲイン量は平版オフセット印刷の平均程度と言えます。
2007年版:編集尺「ver1.1」は、同じ用紙・版式でもって、133線に変更しました。線数を下げたことによって画像類の精細さは及びませんが、この版式で133線だとドットゲインが殆ど生じず、印刷結果の網点は、理論値とほぼ等しくなっています。
通常、書籍印刷で使われるのは平版オフセット印刷が多いことや、同じ版式であっても紙や印刷機材などによって印刷結果は変化することから、印刷会社の方に必ずご相談ください。
- 「級」「ミリメートル」「インチ」「ポイント」の換算比率の一覧表です。
- A系列・B系列および代表的な書籍寸法を表にしました。
A4およびB4を太字にしてあります。
- ミリメートル基準の、さまざまな太さの罫線です。
- インチの目盛りを、色を変えてセンチメートルの目盛りと重ねて載せました。
※一般にインチ尺は16等分されており、「4分の3インチ」「8分の7インチ」などの表記をもちいます。
- 1目盛りが4ポイント、つまり「72分の4インチ目盛り」になっており、「4字分の幅=ポイント数」になる定規です。これを使うことで、オモテ面の「簡易級数表(センチメートル定規)」同様に、目盛りだけで簡易ポイント表として使えるわけです。
目盛りの名前は「x4pt」となっています。
※ DTPにおけるポイントは正確に72分の1インチ(端数なし)なので、(インチを72で割って)端数の出る活版印刷時代のポイント(おもに「アメリカンポイント」と)とは、ことに大きな数値において若干の誤差が出てきます。
- A1からA8あるいはB1からB8の、各サイズの関係が直感的にわかります。
用紙取り計算などの参考にお使いください。 - 角型・長型のそれぞれ1号から4号の封筒と、A・B系列の用紙とのサイズの一覧です。
数字と、直感的なサイズの両方がわかります。
本や書類を梱包する際に便利です。
- ポイント基準の、さまざまな太さの罫線です。
ポイントを使ってレイアウトデザインを行う際にお使いください。